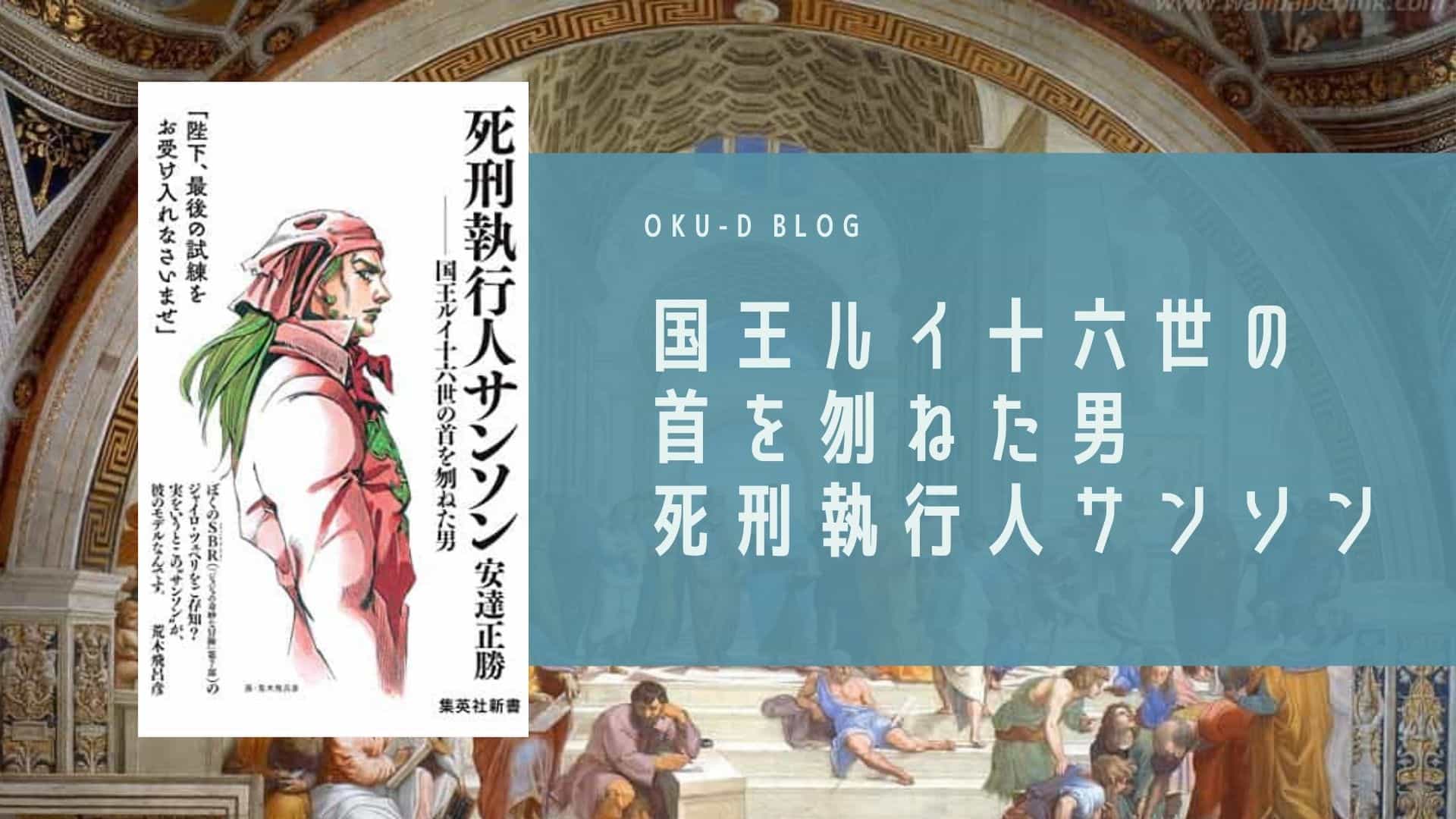
呪われた一族
人類史に残る転換点としてフランス革命はアンシャンレジーム(旧体制)を打破したと言われる。旧体制(封建制)とは、硬直した身分制度である。国王の子は国王になるし、処刑人の子は処刑人を引き継がなければならなかった。

民衆を導く自由の女神
穢らわしいものに触れたら人は洗い流したくなる。触れたくないし忌み嫌う。好き好んで処刑を生業とするものがいるだろうか。
誰もやりたくないが誰かがやらなければならない。必要悪として処刑人一族は、町はずれにひっそりと暮らしていた。
不可触賤民の扱いで、人々は処刑人を怖がり、軽蔑もした。社会からの支援も得られにくい。そんな存在であった。
本書は、呪われた一族の4代目シャルル・アンリ・サンソンの奇妙な物語について描かれた作品だ。
最近だとFate/Grand Orderにもキャラ化されているので知っている人もいるかも。

シャルル・アンリ・サンソン
サンソンは、敬虔なカトリック教徒として、愛する国王を信じつつ、啓蒙主義の影響も受け、自身の生業である処刑の廃止を夢見た人物である。
そんな彼がフランス革命という激流をどのように渡っていったのか。フランス革命の裏主人公とも言えるサンソンの活躍を追っていこう。
賢王ルイ十六世に夢見るサンソン
一流の処刑人一族だったサンソンは、地元では顔が割れているので、パリから百キロ以上離れたルーアンの学校に寄宿した。
一年目は良い学生として評判で周囲とも上手くやっていたが、二年目に処刑人一族とバレてしまう。
それを期にサンソンに対していじめが起き、生徒の親からも退学させるよう圧力がかかり、やむなくパリへ帰ることに。
そこで家庭教師を雇うことにした。その師がグリゼル師という人物で変わった神父であった。聖書をすべて暗記し、その教えを余すことなく弟子へ伝えた。
後年、裁判にてサンソンが弁護士にも勝つほどの力を持てたのはグリゼル師のおかげだろう。
まもなく敬愛していた師と父がなくなり、たったの十五歳で後を継ぐことになった。
その後、ルイ十六世、マリー・アントワネットと後に自分が処刑する王族たちにも謁見し、交流を深めていくうちに、国王に対する敬愛の念をもつようになったサンソン。
当代随一のインテリであり、理性のあるルイ十六世の治世の下ならば、啓蒙を推し進め、より良い社会になるだろう。
ヴォルテールも願った死刑の廃止。己の生業である処刑のない世界になるのではないだろうか。小さな希望を胸に秘めたサンソンだが、フランス革命の足音が近づいてきた。
市民に殺しの方法を相談され苦悩するサンソン
ヴァレンヌ逃亡事件で市民のルイ十六世に対する信頼は失墜した。愛する王様はもう死んだのだ。悪逆非道な王は殺さなければならない。
革命後、空気は一変した。これまで甘い汁を吸ってきた特権階級(貴族と高位聖職者)に血の代償を求めたのだ。
処刑人一族だけでは到底まわせない程、処刑のニーズが急騰。ギロチンなど使ったことがない市民は、使い方を教えてもらおうとサンソンの下を訪れる。
ギロチンを扱うには技術が求められ、決して簡単ではない。サンソンですら一発で成功しないこともあるのだ。
ギロチンでの生々しい処刑を行い、極度の緊張状態から脳卒中起こして死んでしまう市民もいた。プロの処刑人とは違い、人の命を扱う重圧には慣れていない。
しかし革命の空気は特権階級に対して報復することは許されると思い、市民は虐殺を実行していった。
処刑人としてプロ意識
処刑のプロとしてサンソンは怒っていた。たしかに自分も処刑してきたし数で言えば相当数、処刑している。しかし、それは裁判によって正式な手続きを得たあとに実行したものだ。
何の資格があって、人々は虐殺するのだろうか。行き場のない怒りをぐっと堪えるサンソンであった。
最強貴族ハプスブルク家率いるオーストリア軍に迫られた恐怖から市民の虐殺はきていたが、ヴァルミーの戦いの勝利で興奮状態が収まった。
ここから新時代が始まるのだ。ゲーテはこう述べている。

ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ
この日、この場所から、世界史の新しい時代がはじまる
ヴァルミーの戦い後、世界初の普通選挙で選ばれた国会が開かれ、王政廃止を宣言した。
ルイ十六世の裁判
外敵は追い払い、ルイ十六世の裁判が始まった。マリー・アントワネットはハプスブルク家出身でフランス側の情報を流していたため、王への疑念は払拭されない。
革命の大天使サン・ジュストの演説が裁決を下した。初演説だったというのに驚きだ。

サン=ジュスト
いかなる幻想、いかなる慣習を身にもとっていようとも、王政はそれ自体が永遠の犯罪であり、この犯罪に対しては、人間は、立ち上がって武装する権利を持っている。
王政は、一国民全体の無知蒙昧さによっても正当化され得ない不法行為の一つである。
そういう国民は、王政容認という実例を示したがゆえに、自然に背いた罪人なのである。
すべての人間はいかなる国においてであれ、国王の支配を根絶すべき秘密の使命を自然から受けている。
人は罪なくして国王たりえない。これは、明々白々なことである。国王というものは、すべて反逆者であり、簒奪者である
絶対に逆転しないはずの身分が覆った。国王が国王ゆえに罪人とされたのだ。国王の処刑が決まり、心落ち着かないサンソン。それもそのはず。処刑をするのはサンソンしかふさわしくないのだから。
ルイ・カペーの処刑
国王の処刑に対する正当性の確信がもてず、己の生業含めアイデンティティを失ってしまう。
革命は、あきらかに、行き過ぎてしまった。
先祖代々受け継がれてきた仕事は、歴代国王の代わりに犯罪を罰してきた誇りがある。
国王陛下に手をかけるなんてとんでもないことではないか。職務放棄するか?それは名誉に傷がつくのでできない。でもどうするべきか。
整理のつかないまま処刑当日の朝を迎える。
まとめ
ここからクライマックスに入り、国王の処刑の日が近づいてくる。人間味溢れるサンソンの葛藤が克明に描かれる。一番いいところなので気になった人は是非読んでみてほしい。
おすすめ本
↑今回の書評本(死刑執行人サンソン)はこちら
↑ベルばらの池田先生が語るフランス革命
↑池田先生がフランス革命に関わる女性陣について語った一冊


